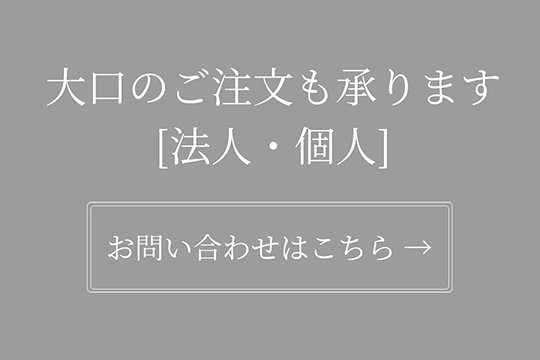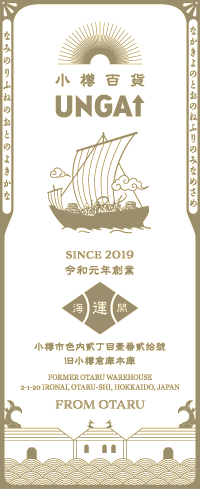【第10話】ローソクの灯りの似合う町
小樽市総合博物館 館長 石川 直章
2021.4.10 更新
小樽に心を寄せる人々であれば、ローソクから連想するのは2月の厳寒期に行われる「小樽雪あかりの路」であろう。
「雪あかり」とは、積雪に灯火がうつり、周囲が薄明るくなることで、冬の季語ともなっている。
つまり日本の積雪地帯においてはどこにでも起きうる現象であるが、儚く脆いその語感は小樽の持つもうひとつのイメージに合うものである。
そもそも、このイベントの名前は、小樽出身の作家、伊藤整(1905−1969)が大正14(1925)年に出版した最初の詩集『雪明りの路』にちなんで名付けられたものである。
序文の「之が今までの私の全部だ。なんといふ貧しさだらう。(中略)私はまた之からこの詩集を懐にして独りで歩いて行かなければならない。頼りないたどたどしい路を歩いて行かなければならない。」とあるように、若き詩人のひそかな自信の裏に、緊張と不安を抱きながら出版された詩集であった。
この詩集に描かれる光景は、伊藤整の心の中で描かれた小樽の光景であったのだろう。
小樽は、明治期以来、新興経済として発展し、多くの作家たちが北海道視察の際に立ち寄る場所となっていた。
小樽文学館前館長、亀井秀雄によれば、小樽を舞台にした文学作品は、1876(明治9)年、三条実美の「小樽八景」からである。
2018年の段階で、小樽図書館所蔵作品に絞っても100を超える作品を見ることが出来る。
特に運河論争前後から、「斜陽の町」と歴史資産に注目が集まり、作品の舞台としては格好の場所となったことも作品数が多い理由の一つである。
かつて、小樽に残る文化遺産を総合的に保存していくための『小樽市歴史文化基本構想』編纂の業務に携わったことがある。
この時に、全国的にも「文学が生まれる町」という特色を持っている小樽、という側面をアピールするため、報告書の各章の扉に「小樽を表す文学作品の一節」を掲げた。
選出は小樽文学館の玉川館長にお願いした。
その中に小樽の地形と歴史を見事に表現した一文があった。
小林多喜二の「故郷の顔」の一節である。
「人口十五六万の、街並が山腹に階段形に這い上った港街で、広大な北海道の奥地から集まってきた物産が、そこから又内地へ出て行く謂わば北海道の『心臓』みたいな都会である。」
この作品が発表された昭和7(1932)年、昭和恐慌の中にあっても、小樽は物流の拠点として繁栄を謳歌していた。
その「光」の部分を表現した一文で、のちに日本遺産地域型への申請時に「北海道の心臓と呼ばれた町」というタイトルにもなった(申請は未認定)。
しかし、この文章の中核は以下に続く部分にある。
「時代的などんな波の一つも、この街全体が、恰かも一つの大きなリトマス試験紙ででもあるかのように、何等かの反応を示さずに素通りするということはない。」
小樽は繁栄を極め、成功した資産家たちも多く生まれたが、その波に乗り切れなかったもの、落後していくものも多く存在した。
明治以降、「近代化の実験室」として不都合なことも数多く生みながら、発展を目指す姿が描かれているからである。
小林多喜二の文章では、さらにその「影」の部分に触れている箇所がある。
昭和5(1930)年、治安維持法などの容疑で起訴され、豊多摩刑務所に収容された小林多喜二が、村山籌子にあてた手紙の一部である。
「冬が近くなると、ぼくはそのなつかしい国のことを考えて深い感動に捉えられている。そこには運河と倉庫と税関と桟橋がある。そこでは人は重っ苦しい空の下を、どれも背をまげて歩いている。ぼくは何処を歩いていようが、どの人をも知っている。赤い断層を処々に見せている階段のように山にせり上がっている街を、ぼくはどんなに愛しているか分からない。」
華やかでも抒情的でもない、小樽の市井の人々の光景を「愛している」多喜二が描いている。
「影」の部分があるからこそ、光を強く感じることができる。
小樽に暮らす人間は誰しも感じる風情である。