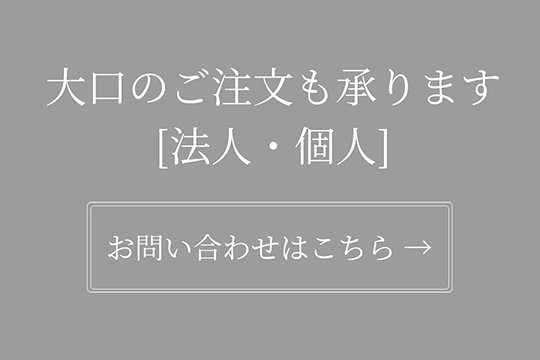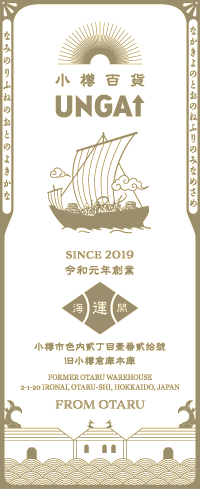【第11話】縄文土器 〜北海道考古学発祥の地 手宮公園下遺跡〜
小樽市総合博物館 館長 石川 直章
2021.9.28 更新
北海道考古学発祥の地 手宮公園下遺跡
小樽、北海道における、最初の「縄文土器」の報告は、明治11年(1878年)7月26日、米国人の生物学者エドワード・S・モースによって行われた。「モース」の名前に聞き覚えのある方もいると思う。日本史の教科書に「大森貝塚を発見した考古学者」として登場している。「縄文土器」という名前はモースが東京大森貝塚の調査報告で使用した「cord marked pottery」に由来する。
現在の研究では、縄文時代≒縄文土器の製作年代はおよそ16,000年前から開始され、北海道では「続縄文土器」にかわるBC300年ころまで続いた。縄文土器の特徴は、なんといっても「縄文」にあるが、土器の表面に「縄」状のものを押し付ける制作方法は、世界的には珍しくはないが、「縄」状の工具を土器の表面で転がして文様とする技法は、日本列島独自のものといってよいだろう。
では、縄文土器は何の用途に使ったものなのだろうか?現在の研究では、列島で独自に発生したと思われるが、その主目的は「煮炊き」にあった。それまでの旧石器文化では、「焼く」という調理法は存在したが、ドングリなどの固い木の実を食べる方法は無かった。土器の発明は、それまでの肉、魚にくわえ植物性の食糧の利用を可能にした、画期的なものだった。食糧となる資源の増加は、人口の増加をもたらし、日本列島各地に多くの遺跡を残すようになる。
「煮炊き」に使用するため(それ以外の用途の土器も中期以降増加する)、「鍋」としての機能に特化していくはずなのだが、これも縄文文化の特色の一つで、装飾的な器形や、過剰ともいえる文様が土器にほどこされている。しかし、やはり基本は鍋であった。そのために熱効率の良い形に進化していく。それがゆるやかに上方に開く円筒形の形だ。現在では「鉢」に近い形なのだが、縄文時代の生活では、この形こそが最も機能的なものであった。
それは、熱源が「炉」つまりイロリであったからだ。炉の中央に置き、そこからではなく、周囲から熱を吸収しやすいような、ずん胴な形こそが重要であった。
総合博物館運河館に展示している縄文土器(およそ3,500年前)をよく見ていただくと、土器の下半分が熱によって赤く変化したものや、ススのついたものがあることがお分かり頂けるだろう。実は、中には土器の内側に「おこげ」のついたものもある。現在、全国の縄文土器の「おこげ」を化学的に分析し、同位体などの違いから「何を食べていたのか」を探ろうとする研究もはじまっている。
初めに紹介した、明治11年のモースの調査は、北海道で始めての学術的発掘調査であると思われる。場所は、手宮公園の南側の斜面、現在は「手宮公園下遺跡」と呼ばれている。30年ほど前に行われた発掘調査では、縄文時代前期後半から中期前半(今から6500年ほど前)の大量の土器や石器が発見され、また全国に例のない形をした装飾品が出土していた。土器片など30万点近い「密度」は現在のところ小樽では群を抜いて高いものである。土器片の量から、ある程度の人数の集落が一定期間存在したことは間違いなく、小樽最初の「ムラ」といえる。
また、小樽の郊外には縄文時代後期(およそ3500年前)のストーンサークルが残されている。縄文時代の人々がつくった大きな構造物を、目の前で見ることができる、貴重な遺跡である。ぜひ、現地でその姿を見ていただきたい。
現地に行かれると、山と畑に囲まれ、海を見ることはできないが、ストーンサークルがつくられたころ、JR蘭島駅付近には大きな入江があり、そこから川をさかのぼった高台の上であったことが地質調査でわかっている。そしてその川の岸辺からは、大量の土器や木で作った道具、そして巨大な柱などがみつかった。この岸辺付近は「忍路土場(おしょろどば)遺跡」とよばれ、運河館にはこの遺跡から出土した土器や木製品が展示されている。
土器は「台所用品」である。この器で何を煮て、どんな料理を作っていたのだろうか?そんな想像をめぐらしながら土器を見てみてはいかがだろう。